top of page
検索


vol.281【傷寒論】太陽中風と太陽傷寒の違いを鍼灸で診る
同じ「太陽病」のくくりに入りながら、なぜ『傷寒論』では「太陽中風」と「太陽傷寒」が明確に分けられているのか──。 その違いを表すのは、単なる病名や処方の違いではなく、氣の動きと衛氣の状態、そして“身体の守り”の違いである。...

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 4分


vol.273【難経第七十八難】脈の強弱は、病の深浅を示す〜“鼓動”から読む身体の物語〜
手を当てたとき、何を感じるか——。 それが、鍼灸家としての“深さ”を決める。 『難経』第七十八難では、脈の強弱(浮沈・大小・緩急)が いかに病の深浅・軽重を示すかを、明確に説いている。 脈は単なる“拍動”ではない。 それは、氣血の声であり、臓腑の息吹であり、...

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 5分


vol.257【難経第六十二難】脈と氣の虚実とは?〜“拍動が語る内なる氣の状態”〜
脈は、氣の声である。 力強く打つか、細く沈むか。 そこに、 氣の充実・不足・停滞・逆乱といった“内なる氣の状態”が如実に現れる。 『難経』第六十二難は、 脈診を通じた“氣の虚実”の見極めと、それに基づく施術方針”について明快に語っている。 【1....

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 4分


vol.253【難経第五十八難】脈の変化と五臓の関係とは?〜“虚実のサイン”を脈に聴く〜
脈は、内臓の言葉。 『難経』第五十八難では、 五臓の氣血の虚実が脈にどう表れるか を明確に示している。 つまり──脈を読めば、臓腑の状態がわかる。 これは東洋医学において、最も繊細かつ深遠な“診察の術”である。 【1. 五臓と脈の対応関係】 古典的な脈の配置:...

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 4分


vol.252【難経第五十七難】脈に現れる氣血の異常とは?〜“寸・関・尺”に映る内なる変化〜
脈は、氣血の声。 東洋医学において、脈診は単なるバイタルチェックではなく、 氣と血の状態、五臓六腑の調和を“触れて診る”術 である。 『難経』第五十七難では、 脈と氣血の関係性、特に寸・関・尺の三部に映る氣血の異常 について説かれている。 【1. 寸・関・尺とは何か】...

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 4分


vol.244【難経第四十九難】なぜ左手と右手で診るのか?〜陰陽と臓腑配当の秘密〜
左手は心を、右手は肺を。 鍼灸師なら誰もが知る“左右の脈の違い”。 だが、その根拠はどこにあるのだろうか? 『難経』第四十九難では、脈診における「左右の手の配当」について明確に述べられている。 それは単なる慣習ではなく、 陰陽と臓腑の哲学に基づいた診断体系 なのだ。 【1....

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 4分


vol.243【難経第四十八難】脈と氣の違いとは?〜脈状と氣状の見分け方〜
脈を診るとき、我々が見ているのは「血」か、「氣」か。 『難経』第四十八難では、“脈状”と“氣状”という二つの概念を対比しながら、 その本質的な違いに切り込んでいる。 つまり、 同じ脈の打ち方であっても、それが「氣の乱れ」か「血の滞り」かを見極めなければならない...

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 4分


vol.242【難経第四十七難】“氣口”とは何か?〜寸口脈診の本質〜
脈を診る──それは、氣を診ること。 『難経』第四十七難では、東洋医学における代表的な脈診部位、 すなわち**「氣口(きこう)」=寸口の脈**について深く掘り下げられている。 寸口とは、単なる血流の拍動点ではなく、 氣の状態が最も如実に現れる“生命の窓” なのだ。 【1....

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 4分


vol.224【難経第二十九難】脈は「どこで診るのが正解か?」〜三部九候と臨床定位〜
脈を診るとき、「どこで診ていますか?」と聞かれたら、どう答えるだろう。 橈骨動脈の寸・関・尺? それとも手首の内側全体? 『難経』第二十九難は、脈診における“部位の選択”に焦点を当てる。 それは単なる部位の話ではなく、 診断の精度と深度 に直結する“定位”の哲学である。...

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 4分


vol.223【難経第二十八難】“脈の虚実”は何を診るのか?〜手応えで読む氣血の力〜
脈を触れたとき、あなたは何を感じ取っているだろうか? 「強い」「弱い」「弾む」「沈む」……脈には多くの情報が詰まっている。 中でも『難経』第二十八難が示す「虚実」は、氣血の盛衰を直観的に測る診断の要だ。 では“虚の脈”とは何か? “実の脈”とはどう違うのか?...

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 4分


vol.222【難経第二十七難】脈の「動く」と「止まる」は何を意味する?〜氣血の瞬間診断〜
患者の脈に触れたその瞬間、「あれ?」と違和感を抱いたことはないだろうか。 一定のリズムで流れるはずの脈が、突如として止まり、数息のあいだ動かなくなる。あるいは、妙にせかせかと速く、浮ついたように感じられる脈。 こうした“瞬間的な変化”に、術者はどう向き合うべきなのか?...

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 5分


vol.221【難経第二十六難】氣の多少はどこで測る?〜診断と脈の深さ〜
"氣"という目に見えない存在を、私たちはどうやって捉えるのか。東洋医学の診断法において、氣の多少は重要な指標のひとつ。しかし、それを“どう測るか”という問いには、現代でもなお答えが求められている。『難経』では、氣の多少は"脈の深浅"によって測るべきだと説かれている——。今回...

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 5分
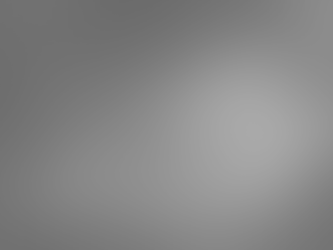

vol.215【難経二十難】“心は君主の官”とは?〜思考・意識・魂を司る氣の中心〜
「心が乱れると、氣が乱れる──氣が乱れると、身体が壊れる」 古来より東洋医学では、「心」を五臓の中でも特別視してきた。 その理由こそが、難経第二十難に記された“君主の官”という表現にある。 本稿では、 “心の氣”とは何か? そしてなぜ“心”が氣の中心に位置づけられるのか、...

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 5分


vol.208【難経十三難】氣口・人迎の診察とは?〜頸動脈の“氣”をどう読むか〜
「人迎と氣口、どちらが強いですか?」 東洋医学の古典において、脈は手首だけではない。 頸部の動脈──すなわち**人迎(顎の下)と氣口(橈骨動脈)**は、全身の氣を測るための“陰陽のゲート”として扱われていた。 難経十三難では、この 二つの脈の強さの比較 から、...

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 5分


vol.207【難経十二難】脈診の左右差に意味はあるか?〜左右の氣のバランス診断〜
「左右の脈が違うのって、なぜなんですか?」 脈診をしていて、多くの臨床家が感じる疑問。 難経第十二難では、 左右の脈における陰陽の違い が明示されている。 それは単なる解剖学的な差ではなく、 氣の偏り=バランスの乱れ として読むべき現象である。 【1....

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 5分


vol.206【難経十一難】臓腑の病は脈にどう現れるか?〜氣の状態と五臓六腑の関係〜
「この脈、どの臓腑の乱れでしょうか?」 臨床でよく聞かれるこの問い。 東洋医学では、 “氣”は臓腑を通じて脈に映し出される と考えられている。 難経第十一難は、 氣・臓腑・脈 をつなぐ東洋診察の核心を示す一章である。 【1. 臓腑と脈は“氣の写し鏡”】...

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 5分


vol.205【難経十難】脈の浮沈遅数とは?〜氣の性質を読み解く診察力〜
「浮いてる脈、沈んでる脈って、何が違うんですか?」 脈診を学び始めると、最初に出てくる“浮・沈・遅・数”という言葉。 だが、ただ手首を触って分類するだけでは、その意味はつかめない。 難経第十難 は、脈という“氣の表現”の奥行きを教えてくれる。 【1....

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 5分


vol.204【難経九難】寸口三部の脈診とは何か?〜手首に映る全身の氣〜
「脈を診るって、結局どういうことですか?」 東洋医学を学び始めた者から、臨床ベテランまで── 常に問い続けられるこのテーマ。 難経第九難では、古来から伝わる「寸口三部」の概念が語られる。 それは単なる“手首の脈”ではない。 氣の海原を、三つの窓から観る診察法 である。...

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 5分


vol.203【難経八難】臓腑と経絡の“主治関係”〜氣の通り道とその役割〜
「経絡って、ただの“道”なんですか?」 臨床でも頻繁に使う“経絡”という言葉。 しかし、その本質にどこまで迫れているだろうか? 第八難は、臓腑と経絡の“主治関係”──つまり「氣の通り道の意味」を明らかにしてくれる。 【1. 経絡は“氣の文法”である】...

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 5分


vol.200【難経五難】気血津液とは何か?〜生命を支える“三宝”の捉え方〜
「氣はわかるけど、血や津液って何なの?」 東洋医学では、氣だけでなく「血(けつ)」と「津液(しんえき)」を重視する。 この三者は、生命活動の“三宝”ともいえる基本構成要素。 第五難では、この“氣血津液”をどのように捉えるべきかが語られる。...

- 鍼仙人 - 高山 昌大
読了時間: 5分
bottom of page




